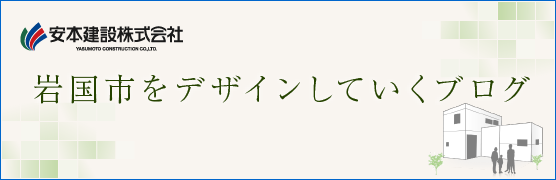2025年省エネ基準義務化!わかりやすく解説・変更点と影響
投稿日: 2025.04.17
新築住宅を検討する際に、耳にする機会が増えている「省エネ基準」。
一体どのような基準で、家を建てる際にどのような影響があるのでしょうか? この基準を理解することは、快適で経済的な住まいを実現するために非常に重要です。
今回は、省エネ基準の基礎知識から、2025年の改正と義務化について、できるだけ分かりやすく解説します。
専門用語も丁寧に説明するので、安心して読み進めてください。
これから家づくりを始める方にとって、役立つ情報が満載です。
省エネ基準の基礎知識
省エネ基準とは何か
省エネ基準とは、建築物省エネルギー消費性能基準のことです。
国は、地球温暖化対策や脱炭素社会の実現を目指し、住宅の省エネ性能に関する規制を強化しています。
この基準は、住宅の断熱性能や気密性能、エネルギー消費量などを評価するための指標を提供しています。
2025年からは、新築住宅への適用が義務化されます。
省エネ基準を満たすための指標:UA値とηAC値
省エネ基準を満たしているかどうかを判断する上で重要な指標がUA値とηAC値です。
UA値は、建物の外皮(壁、屋根、窓など)から逃げる熱の量を表し、数値が小さいほど断熱性能が高いことを示します。
ηAC値は、夏場の窓からの日射熱の取得量を表し、数値が小さいほど日射熱の影響を受けにくいことを示します。
これらの値が基準を満たすことで、省エネ性能が確保されます。
一次エネルギー消費量とは
一次エネルギー消費量とは、住宅を建てるために必要なエネルギーの総量を表します。
これは、電力、ガス、灯油などの二次エネルギーを、それぞれのエネルギー源(石油、天然ガス、太陽光など)に換算したものです。
一次エネルギー消費量が小さいほど、省エネ性能が高いと評価されます。
省エネ基準適合住宅の種類:ZEH、LCCMなど
省エネ基準にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる性能レベルが設定されています。
代表的なものとして、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、LCCM(ライフサイクル・カーボン・マイナス・ハウス)などがあります。
ZEHは年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指した住宅で、LCCMは住宅のライフサイクル全体でのCO2排出量をマイナスにすることを目指した住宅です。
その他にも、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅などがあります。
これらの住宅は、それぞれ異なる基準を満たすことで認定されます。
省エネ基準に適合するメリットとデメリット
省エネ基準に適合した住宅には、光熱費の削減、快適な居住環境、環境への貢献といったメリットがあります。
しかし、高性能な断熱材や設備の導入が必要となるため、初期費用が高くなるというデメリットもあります。
メリットとデメリットを比較検討し、ご自身のライフスタイルや予算に合った選択をすることが重要です。

2025年からの省エネ基準の改正と義務化
2025年以降の省エネ基準の変更点
2025年以降、省エネ基準が改正され、新築住宅への適用が義務化されます。
改正内容としては、UA値やηAC値、一次エネルギー消費量に関する基準が厳しくなることが挙げられます。
具体的には、断熱性能や気密性能の向上、高効率な設備の導入などが求められます。
改正による住宅建設への影響
省エネ基準の改正と義務化により、住宅建設費用が高くなる可能性があります。
高性能な建材や設備の導入が必要となるためです。
しかし、長期的に見ると、光熱費の削減によって費用を回収できる可能性も高いです。
義務化に伴う費用負担と補助金制度
省エネ基準への適合には、追加費用が必要となるケースが多いです。
しかし、国や地方自治体による補助金制度を利用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。
補助金の利用条件や申請方法については、事前に確認しておきましょう。
改正後の省エネ基準への対応策
2025年以降の省エネ基準に適合するためには、設計段階から省エネ性能を考慮した計画が必要です。
建築業者とよく相談し、最適な建材や設備を選定することが重要です。
また、補助金制度の活用も検討しましょう。

まとめ
この記事では、省エネ基準の基礎知識から、2025年の改正と義務化について解説しました。
省エネ基準は、快適な住まいを実現し、環境にも配慮するための重要な基準です。
UA値やηAC値、一次エネルギー消費量といった指標を理解し、ご自身のライフスタイルや予算に合った住宅を選びましょう。
2025年からの義務化に伴い、費用負担が増える可能性がありますが、補助金制度の活用も検討することで、負担軽減を図ることが可能です。
新築住宅を検討する際は、省エネ基準について十分に理解した上で、建築業者と綿密な打ち合わせを行うことが大切です。
快適で経済的な、そして環境にも優しい住まいづくりを目指しましょう。