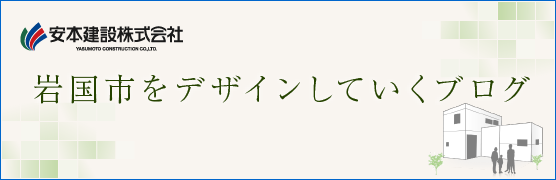2025年建築基準法改正とは?わかりやすく変更点を解説
投稿日: 2025.04.24
2025年4月、建築基準法が改正されます。
この改正は、私たちの暮らしにどのような影響を与えるのでしょうか? 新築やリフォームを検討されている方、あるいは現在住宅をお持ちの方にとって、改正内容を理解することは重要です。
この改正によって、住宅の安全性や省エネルギー性能、そして建築コストなどに変化が生じます。
今回は、2025年建築基準法改正の主なポイントを、できるだけ分かりやすくご紹介します。
改正の背景や目的、具体的な変更点、そして私たちが今後どのように対応していくべきかについて、解説します。
2025年 建築基準法改正 わかりやすく解説
改正の背景と目的
2025年建築基準法改正の背景には、2050年カーボンニュートラル目標の達成があります。
建築物は、日本のエネルギー消費の約3割、木材需要の約4割を占めるため、省エネルギー化と木材利用の促進が不可欠です。
改正は、これらの目標達成に向けた重要な取り組みの一つです。
具体的には、地球温暖化対策の強化、木材利用の促進、そして既存建築物の長寿命化などが目的として挙げられています。
省エネ基準の義務化とは
改正後は、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準の適合が義務化されます。
これまで大規模建築物などに限定されていた省エネ基準が、全ての建物に適用されることになります。
これにより、建物の断熱性能や気密性能が向上し、エネルギー消費量を削減することが期待されます。
省エネ基準に適合しない場合は、建築確認済証が発行されず、着工や使用開始が遅れる可能性があるため、注意が必要です。
4号特例の縮小と影響
これまで小規模建築物の建築確認手続きを簡素化していた「4号特例」は縮小されます。
改正後は、対象範囲が狭まり、多くの建物が従来よりも厳しい審査を受けることになります。
これにより、建築確認にかかる時間や費用が増加する可能性があります。
特に、木造住宅を計画されている方は、改正後の基準を理解し、対応する必要があります。
木造建築物の基準変更
木造建築物については、省エネ化に伴う重量増加に対応するため、壁量基準や柱の小径基準が変更されます。
また、大規模木造建築物の防火規定も緩和され、木材の露出仕上げが可能になります。
これにより、デザイン性の高い木造建築物の建設が促進されるでしょう。
さらに、中層木造建築物の耐火性能基準も一部緩和されます。
その他重要な改正点
既存不適格建築物(現行基準に適合しない建築物)については、一定の条件を満たす場合、現行基準を適用しない規定が追加されます。
また、二級建築士の業務範囲も拡大されます。

改正によるメリットとデメリット
改正によるメリット
改正によるメリットとしては、住宅の品質向上、耐震性向上、環境負荷軽減などが挙げられます。
省エネ基準の義務化により、環境に優しい住宅が増え、光熱費の削減にも繋がります。
また、4号特例の縮小によって、住宅の品質や安全性が向上する可能性があります。
改正によるデメリット
一方で、リフォーム費用や期間の増加、デザイン性の制限などがデメリットとして挙げられます。
省エネ基準への適合には追加費用が必要となり、リフォーム期間も長期化する可能性があります。
また、構造計算の厳格化により、デザイン性の高い建築物が建てにくくなる可能性もあります。
今後の対応について
2025年4月以降に建築物を新築・改築する際は、改正後の基準を満たす必要があります。
建築計画を立てる際には、事前に改正内容を十分に理解し、専門家への相談も検討しましょう。
特に、リフォームを検討されている方は、改正による影響を事前に把握しておくことが重要です。

まとめ
2025年4月の建築基準法改正は、省エネルギー化と木材利用の促進を主な目的としています。
省エネ基準の義務化や4号特例の縮小など、多くの変更点があり、新築やリフォームを検討する際には、改正内容を十分に理解する必要があります。
改正によって、住宅の安全性や環境性能は向上する一方、コストや工期が増加する可能性もあります。
計画段階から改正内容を考慮し、専門家と相談しながら、適切な対応を検討することが重要です。
改正によって、住宅の安全性や環境性能は向上する一方、コストや工期が増加する可能性もあるため、計画段階から改正内容を考慮し、専門家と相談しながら、適切な対応を検討することが重要です。
この改正は、持続可能な社会に向けた重要な一歩と言えるでしょう。