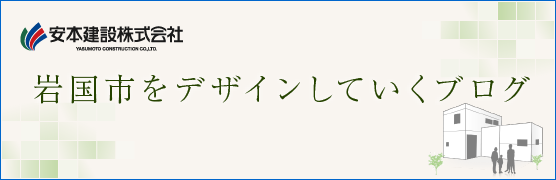建築関係者必見!2025年省エネ法改正の変更点と影響
投稿日: 2025.05.01
2025年4月、省エネ法が改正されました。
この改正は、建築業界に大きな影響を与えます。
新築・増改築を計画している方、あるいは建築に関わる事業者の方にとって、改正内容を正しく理解することは不可欠です。
今回は、改正の背景から具体的な変更点、そして今後の展望まで、分かりやすく解説します。
複雑な法律用語は避け、平易な言葉で説明しますので、専門知識がなくても安心して読み進めていただけます。
省エネ法改正2025の概要と背景
改正の目的と背景にある社会情勢
省エネ法改正の根本的な目的は、建築物分野におけるエネルギー消費量の削減と、カーボンニュートラルの実現です。
日本のエネルギー消費量の約3割を建築物分野が占めるという現状を踏まえ、2050年カーボンニュートラル目標達成に向けた取り組みの一環として、この改正が行われました。
地球温暖化対策、温室効果ガス排出量削減といった社会情勢が、改正の背景に強く影響しています。
改正のポイント3点サマリー
2025年4月施行の省エネ法改正の主要なポイントは、以下の3点に集約されます。
・省エネ基準適合義務化の拡大:原則、全ての建築物(規模の小さな建築物など一部例外あり)の新築・増改築において、省エネ基準への適合が義務化されました。
・4号特例の見直し:小規模建築物の建築確認審査の一部を省略できる「4号特例」が廃止され、新たな分類基準が導入されました。
・構造規制の合理化:木材利用促進を目的とした構造規制の見直しが行われ、木造建築物の設計・施工における規制が緩和されました。
過去の改正と今回の改正との違い
省エネ法は、これまでも何度か改正されてきました。
過去の改正では、住宅の省エネ改修促進のための低金利融資制度の導入、住宅トップランナー制度の拡充、省エネ性能表示制度の導入などが行われました。
今回の改正は、それらに加え、省エネ基準適合義務の対象を拡大し、より厳格な省エネ対策を推進するという点で、大きな転換点となっています。

省エネ法改正2025による具体的な変更点と影響
省エネ基準適合義務化の詳細と影響を受ける主体
2025年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物は、省エネ基準に適合することが義務付けられました。
例外として、10㎡以下の新築・増改築、居室を有しない建築物、歴史的建造物などがあります。
この改正により、建築確認手続きにおいて省エネ基準への適合性審査が必須となり、建築主、設計者、施工業者など、建築に関わる全ての関係者が影響を受けます。
4号特例の廃止と新制度への移行
従来の小規模建築物に対する特例である「4号特例」は廃止され、新たな分類基準が導入されました。
これにより、建築確認申請時の審査項目や提出書類が増加するケースがあり、特に小規模建築物の施工に関係する事業者には影響が大きくなります。
構造規制の合理化と木材利用促進への影響
木材利用促進のため、構造規制の合理化が進められました。
具体的には、3階建て以下かつ高さ16メートル以下の木造建築物において、高度な構造計算が不要となるなど、設計・施工の簡素化が図られています。
これにより、木造建築物の普及促進が期待されます。
建築確認手続き・審査プロセスの変更
省エネ基準適合義務化に伴い、建築確認手続き・審査プロセスにも変更が加えられました。
適合性審査の簡素化・合理化が図られる一方、申請件数の増加が予想されるため、関係者は迅速かつ的確な対応が求められます。
増改築における省エネ基準適合の変更点
増改築についても省エネ基準への適合が義務化されました。
ただし、改正前は増改築後の建築物全体が対象でしたが、改正後は増改築部分のみが対象となります。
適用除外となる建築物
10㎡以下の新築・増改築、居室を有しない建築物(車庫、倉庫など)、歴史的建造物、仮設建築物などは、省エネ基準適合義務の適用除外となります。

まとめ
2025年4月施行の省エネ法改正は、建築業界全体に大きな影響を与えるものです。
省エネ基準適合義務の拡大、4号特例の見直し、構造規制の合理化という3つの主要な改正ポイントは、建築物の設計、施工、確認手続きなど、様々な面に影響を及ぼします。
関係者は、改正内容を正確に理解し、適切な対応を行う必要があります。
今回の改正は、カーボンニュートラル実現に向けた重要な一歩であり、建築業界全体の省エネ化を促進する役割を果たすと期待されています。
改正によって、建築物の設計や施工方法、建築確認手続きなどが大きく変わるため、関係者は最新の情報を十分に把握しておくことが重要です。
また、今後、省エネ基準はさらに厳しくなる可能性があるため、継続的な省エネ対策への取り組みが求められます。