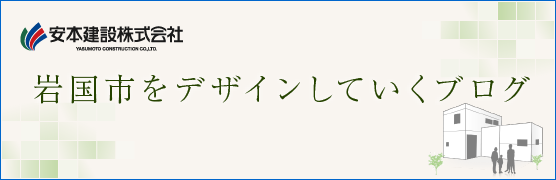2025年の建築基準法改正の影響と対応策をわかりやすく解説
投稿日: 2025.09.18
2025年4月、建築基準法が改正されます。
この改正は、建築業界全体に大きな影響を与えるでしょう。
特に省エネルギー化と木材利用の促進が大きな柱となっており、これまでとは異なる視点での設計や施工が求められます。
今回の改正によって、建築確認申請の手続きや省エネルギー基準への適合などがどのように変わるのか、その概要と建築関係者への影響について見ていきましょう。
新たな基準への対応は、事業の継続や発展に直結する重要な課題です。
早めの準備が不可欠となるでしょう。
2025年の建築基準法改正の概要
改正の背景と目的
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)という目標達成のため、建築物分野における省エネルギー対策の加速化と木材利用の促進が求められています。
建築物分野は、日本のエネルギー消費の約3割、木材需要の約4割を占めるため、これらの分野での対策が、目標達成に大きく貢献すると考えられています。
改正は、こうした背景から行われます。
具体的な変更点
主な変更点は、4号特例の縮小、構造規制の合理化、省エネルギー基準適合の義務化です。
4号特例は、木造住宅の構造審査を簡略化する制度でしたが、改正により対象が縮小されます。
これにより、建築確認申請の手続きが増加する可能性があります。
構造規制の合理化は、高層木造建築物の増加に対応するため、構造計算の簡素化などが行われます。
また、省エネルギー基準への適合は、原則として全ての建築物に義務化されます。
改正による影響
改正により、建築確認申請の手続きの増加、省エネルギー基準への対応に必要なコスト増加、設計図書作成の変更などが予想されます。
特に、これまで4号特例を利用していた木造住宅の建築には、大きな影響が出ると考えられます。

建築関係者への影響と対応策 わかりやすく解説 2025年建築基準法改正
4号特例の縮小と影響
4号特例の縮小により、これまで審査を省略できた木造住宅についても、構造計算や省エネルギー基準への適合性の審査が必要となります。
これにより、建築確認申請に必要な書類が増加し、申請期間の延長やコスト増加が懸念されます。
省エネ基準適合の義務化
全ての建築物において、省エネルギー基準への適合が義務化されます。
一次エネルギー消費量基準と外皮基準(住宅のみ)の両方を満たす必要があります。
基準を満たせない場合は、断熱材の追加や高効率設備の導入など、追加費用が発生する可能性があります。
今後の対応策と準備
改正内容を正確に理解し、早急に社内体制の整備を行う必要があります。
省エネルギー計算や確認申請業務の効率化のため、専門業者への委託なども検討すべきでしょう。
また、BIM(Building Information Modeling)の活用も有効な手段となります。
社員教育やシステム導入計画を早期に立案し、実行していくことが重要です。

まとめ
2025年4月の建築基準法改正は、省エネルギー化と木材利用促進を目的とし、4号特例の縮小、構造規制の合理化、省エネルギー基準適合義務化といった主要な変更点があります。
これらの改正は建築関係者にとって、業務プロセスやコスト、設計思想に大きな影響を与えます。
改正内容を理解し、適切な対応策を講じることで、今後の事業継続と発展につなげることが重要です。
早めの準備と情報収集が不可欠です。
特に省エネルギー基準への対応は、今後の建築業界において重要な課題となるでしょう。